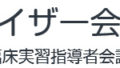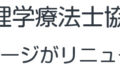理学療法士・作業療法士学校養成施設カリキュラム等改正
カリキュラムの主な見直し内容として、「安全かつ効果的な理学療法、作業療法を提供するために、画像評価を必修化」が組み込まれました。
その他、臨床実習の拡充や管理学の追加などの項目が2020年入学生から適応されています。
画像所見
一般的にはレントゲン画像、CT画像、MRI画像、超音波(エコー)画像などがこれにあたります。
体外から肉眼的に評価ができないものを、特殊な機器を用いて身体内部を視覚化して評価、診断することができます。
脳卒中、肺炎などの炎症所見、骨折、筋や腱板・靭帯などの損傷、心肥大の程度、がんなどの腫瘍、胸水、腹水をはじめ、様々な具体的な診断が行えるようになっています。
リハビリテーション専門職に必要な画像評価
PT・OT・STは診断そのものはできません。
画像評価の重要性は、臨床所見とのすり合わせ、予後予測、リスク管理や運動負荷の決定といったところになります。
脳画像
脳の損傷部位や程度によって、運動麻痺や運動失調、高次脳機能障害の有無が概ね予測できます。また、介入戦略や予後予測の判断材料としても重要になります。
例えば、後頭葉のみが障害を受けているのであれば、運動麻痺が生じる可能性が限りなく低いと思われますが、視覚的な問題(視野障害や遠近感の障害、失認など)が生じる可能性が高いことが予測されます。その際に、動作の安定性が得られない場合には、身体機能評価も重要ですが、視覚要素の評価も十分に実施する必要があるでしょう。
運動器画像
リハビリテーション対象となる方は、運動器疾患の方が多くいらっしゃいます。この場合には、リスク管理が最重要事項となり、運動負荷量の設定や運動方向の制限、動作指導などを実施していく判断材料にもなると思います。
骨折であれば、骨折線(横骨折、斜骨折、椎体の圧潰状況、粉砕型かどうか)の確認、手術の方法(骨接合術の種類や接合部位)や骨の癒合具合(仮骨形成、カットアウトしていないか)の確認が必要です。
軟部組織(筋や腱板、靭帯など)の損傷であれば、MRIや超音波(エコー)などを確認し、他動運動や自動運動が可能かどうか、どの程度の運動負荷にするかなどを主治医に相談していく必要があります。
レントゲンで骨折なしと診断された方で、痛みが続くためにMRIにて詳細な評価を行うと、実は骨折が見つかったというケースも珍しくはありません。患者さんと関わる時間が一番多いのはリハビリテーション専門職ですので、患者さんの状態は十分に把握し、何か問題があれば主治医をはじめとしたチームへの情報共有を行うようにしましょう。
循環器画像
レントゲンでは肺炎像、心胸郭比(CTR)といった心拡大の程度などを確認することができます。さらにCT画像にて細かな評価を行うことが多いです。
肺炎であれば、聴診とあわせての体位排痰法の実施、心拡大を認める方では心機能を確認し、運動負荷や動作方法などの指導を行うための判断材料とします。
超音波(エコー)での評価をする際には注意が必要
近年、リハビリテーション専門職が超音波(エコー)を使用して軟部組織の評価をする機会が増えてきました。これに関しては注意が必要です。
リハビリテーション介入の際に、判断することは問題ありませんが、診断そのものはできません。つまり、患者さんへ説明するとなる場合には、「~が損傷を受けています」、「~が癒着しています」などと言ってしまうと診断となり、医師法違法となる可能性が高いです。
もし、説明を求められた際には、主治医に行っていただくようにすると間違いありませんが、主治医との情報共有はしっかりと行っておきましょう。
おわりに
医療機器の発展とともに、画像評価の重要性も高まってきました。画像評価の方法や臨床応用も学ぶ機会が多くなっております。ぜひとも画像の読み方を勉強していただき、臨床の役に立てられるようにしていきましょう。