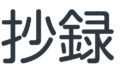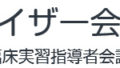症例報告(ケースレポート)について
症例報告(ケースレポート)はリハビリテーション分野において、非常に重要なものとなります。
近年、エビデンスの重要性ゆえに研究論文が重視されているものの、PT・OT・STにおいては、臨床でいかに実践し、どういったことに難渋しているのかということやどのような帰結となったのかということを残していことが大切だと思います。
そういった報告の積み重ねがエビデンスになるのです。
症例報告(抄録)の構成
基本的な構成としては、①「はじめに、背景」、②「目的」、③「症例紹介・提示」、④「経過」、⑤「結果」、⑥「考察」、⑦「結論」となります。
その他、「タイトル(演題名)」、「キーワード」や「倫理的配慮およびプライバシーの保護」といった部分にも注意する必要があります。
「はじめに、背景」
症例報告をするに至った経緯、意義を説明するところになります。他の研究報告に絡めた実践や、まれな症例、複数の疾患を合併した方への工夫、施設独自の取り組みなどを踏まえて記載できるとよいでしょう。
「目的」
症例報告のもっとも述べたい結果と対応するような文面にすることを心がけましょう。
何が解明されていないのか、なぜ今回の症例発表をする必要があったのかを記載します。
「はじめに」や「背景」と合わせて記載する場合も多いので、流れが矛盾しないように記載していきます。
「症例紹介・提示」
症例の情報を可能な限り、基本情報(年齢、性別、身長、体重など)、医学的情報(現病歴、合併症、既往歴、検査所見、画像所見など)、主訴、Needs、社会的情報(家族構成、職業の有無、経済状況、社会資源の利用状況など)を記載する。
また、最後に評価結果(客観的データ)や問題点、理学療法介入の方法などを記載します。
ここで注意する点は、具体的すぎて症例の個人情報が記載されないようにしましょう。
年齢であれば50歳代などとする、発症日はX年Y月、発症日から2日後はY+2日とするなどの工夫が必要です。
「経過」
時系列的にどう変化していったのかを客観的な事実として記載していきます。あまり関係のない要素はいれないように注意しましょう。
「結果」
最終的な帰結がどうなったのかを客観的データとともに示す必要があります。
また、評価結果については、「症例提示」で記載した評価内容と一致した内容が望ましいと思います。結果の場面でいきなり新たな評価が出てくると、比較ができませんし、なぜその評価を記載したのかを再度説明しなければなりません。
「考察」
客観的データから考えられること、先行研究・報告や病態、アウトカムなどと比較してどうだったか、新たに言えることは何かなどを記載します。
本文の内容から、飛躍した考察が記載されている方もいますがこれは良いとはいえません。
考察が矛盾していないか、飛躍しすぎていないかを推敲するようにしましょう。
「結論」
症例を通じて明らかになった点を簡潔に記載する。ここでは、余計な文面は記載しないほうがよいでしょう。
「タイトル(演題名)」について
症例報告の症例やどのような考察、結論に至ったかが分かるように、具体的かつ簡潔に記載する必要があります。
「キーワード」
抄録作成の際には、その報告内容で一番多く出てくるものや報告内容を表しているものとして、3つ程度のキーワードを記載する必要があります。学会のキーワード検索で出てきますので、参考にしましょう。
「倫理的配慮およびプライバシーの保護」
症例報告においても研究発表においても、「倫理的配慮およびプライバシーの保護」は非常に重要であり、これがなければ発表できないといっても過言ではありません。
症例報告であれば、その症例に対して、どのような学会に、どのような発表をするのかということを説明し、書面で同意を得る必要があります。倫理委員会の承認を得ておくことが重要です。
その際に注意が必要なのは、同意の撤回ができること、撤回をしても対象者の治療や入院生活に不利益が被らないことをきちんと説明しておくことも重要です。
おわりに
症例報告は、他のセラピストが参考になる内容も多く、自分自身がまとめていく中でも非常に勉強になるものです。今後、新生涯学習プログラムにおける登録理学療法士制度でも症例検討会の参加が必要になりますし、認定理学療法士でも発表が必須となってきます。 ブロック会や県士会であれば、症例報告も行いやすいと思います。論理的思考の構築のためにも、症例報告を実践していけると良いでしょう。

.jpg)