抄録とは?
抄録とは、要約、Abstract(アブストラクト)ともいい、学会発表や論文投稿をする際に、どのような目的で、どのような方法を用いて、何を発表するのか、そこから何が分かったのか、どのような事が考えられるのかということを凝縮させた文章のことを指します。
つまり、「自分の発表内容を短くまとめたもの」とおもっていただければよいです。
抄録の文字数
短くまとめなければならないといっても、発表する学会によって規定文字数が異なっており、全角換算で600~1200字以内でまとめることが多いと思われますが、図表を用いるものでは最大の文字数も少なくなりますので、演題登録や論文投稿の各規定を十分に確認しておく必要があります。
抄録の重要性
論文投稿の際には、基本的には査読者が確認をし、必要に応じて修正コメントを返信してくれるため完成度の高いものが仕上がると思います。
しかし、学会発表の場合には、抄録査読という形で査読者がつくものの、抄録の良し悪しが採択判断や優秀演題の基準となります。よほど修正が必要の場合には修正依頼があると思いますが、基本的には抄録の出来で採択か不採択かが決まってしまう可能性が高いです。
抄録の構成
- 研究発表は一般的に、①「はじめに、背景」、②「目的」、③「方法」、④「結果」、⑤「考察」、⑥「結論」の構成で作成していきます。
- 症例報告の場合は、①「はじめに、背景」、②「目的」、③「症例紹介・提示」、④「経過」、⑤「結果」、⑥「考察」、⑦「結論」の構成となります。
最近では①を省略するものもあったりしますので、演題登録をするもしくは論文投稿をする際の規定を十分に確認してください。
これ以外にも、利益相反の有無や倫理的配慮について記載が必要となることも多いので、そちらに関しても十分な確認が必要です。
抄録は限られた文字数で、自分の伝えたいことをまとめなければなりません。できる限り、第三者が見ても矛盾しない内容であること、具体的なデータを提示すること、考察が飛躍しないことがポイントとして挙げられます。
自分の発表は自分が一番よく知っていますので、抄録を作成する際にはどうしても主観的解釈になりやすく、他人から見るとよく分からない文章となっていることが多々あります。基本的には、投稿する前に職場の同僚や上司、教員などに確認してもらうと、客観的な視点からの意見がもらえます。
症例報告や研究発表に学会抄録を用いることはすべきでない
一つ注意点があります。
症例報告や研究発表の参考文献に学会抄録を用いている方を見かけることがありますが、これは好ましくありません。
抄録は文字数制限のため、詳細な内容が把握できないこと、また、「抄録では~と記載してありますが、~と訂正させていただきます。」と発表時にデータや結果等の修正をされる発表者もおり、その内容自体が誤っている可能性もあるため、参考文献としては適切でないのです。
参考文献や引用文献として用いる場合には、正式な手順で発表された論文を用いるということを守ってください。
おわりに
リハビリテーション専門職として活躍していくためには、臨床、研究、教育といった三本柱のどれか一つが欠けても、大成しないと思います。
特に、医療現場ではエビデンスをベースとした関わりが非常に重要となりますので、学会への参加や論文の抄読を通して、知識をアップデートしていく必要があるのではないでしょうか。

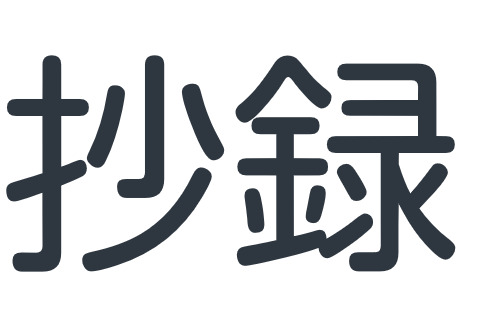

.jpg)